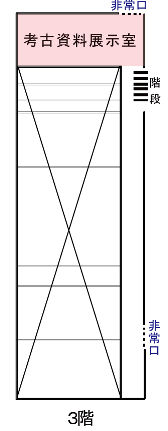土器片(縄文早期・一ツ石遺跡出土)
貝殻を用いた文様がみられる。 |
|

円筒型土器(縄文前期・松林Ⅲ遺跡出土)
大型化していき、文様も複雑化していく。 |
|

深鉢型土器(縄文中期・袰綿遺跡出土)
深鉢型土器は主に煮炊きに使われた大きな土器で、表面に黒いすすがついている。生物と思われるモチーフが見られる。 |
|

深鉢型土器(縄文中期・森の越遺跡出土)
中期独特の大柄な文様と大きさが特徴。 |

浅鉢型土器(縄文中期・森の越遺跡出土)
小型で、貯蔵や盛り付けに使用されたと考えられる。 |
|

甕館(かめかん・縄文中期・森の越遺跡出土)
土器の棺。逆さまで、底がない状態で出土することが多い。 |
|

縄文土器(縄文後期・茂師貝塚出土)
小型化し、繊細な文様に変わっていく。 |
|

注口土器(縄文後期・茂師貝塚出土)
液体を入れ、管状になった部分から注ぐための土器。 |

香炉型土器(縄文晩期・救沢Ⅰ遺跡出土)
香炉を模したと考えられる。晩期は複雑な形の土器が増えてくる。 |
|

弥生式土器(豊岡V遺跡出土)
弥生式土器は縄文土器に比べて固く薄く焼きあがっていることが特徴。 |
|

土師器(古代・大川下町遺跡出土)
古代になると再び大型土器が出現。 |
|
![]()
|

土偶(大川下町出土)
女性の体を模したもので、壊された状態で出土することが多い。 |
|

土偶(大川下町遺跡出土)
妊婦を模している。 |
|

紡錘車(豊岡V遺跡出土)
糸を紡ぐのに使用される道具。 |
|
![]()
|

石斧(せきふ)
斧の先端に付ける石製品。 |
|

石槍(いしやり)
木の柄に装着して突いたり投げたりするもの。 |
|

石匙(いしさじ)
皮などを剥いだりするナイフのようなもの。 |
|

石錐(せきすい)
穴をあけるための道具。 |

石鏃(せきぞく)
矢じり。弓矢の先に装着するもの。 |
|

アメリカ式石鏃
根元部分に切り込みが入った矢じり。 |
|

鰹節(かつおぶし)形石製品(浅内遺跡出土)
鰹節の形に似ていることから名付けられた。糸等を巻き付けたような跡が見られる。 |
|

環状石製品(森の越遺跡出土)
石製の腕輪とみられ、装飾品と考えられる。 |